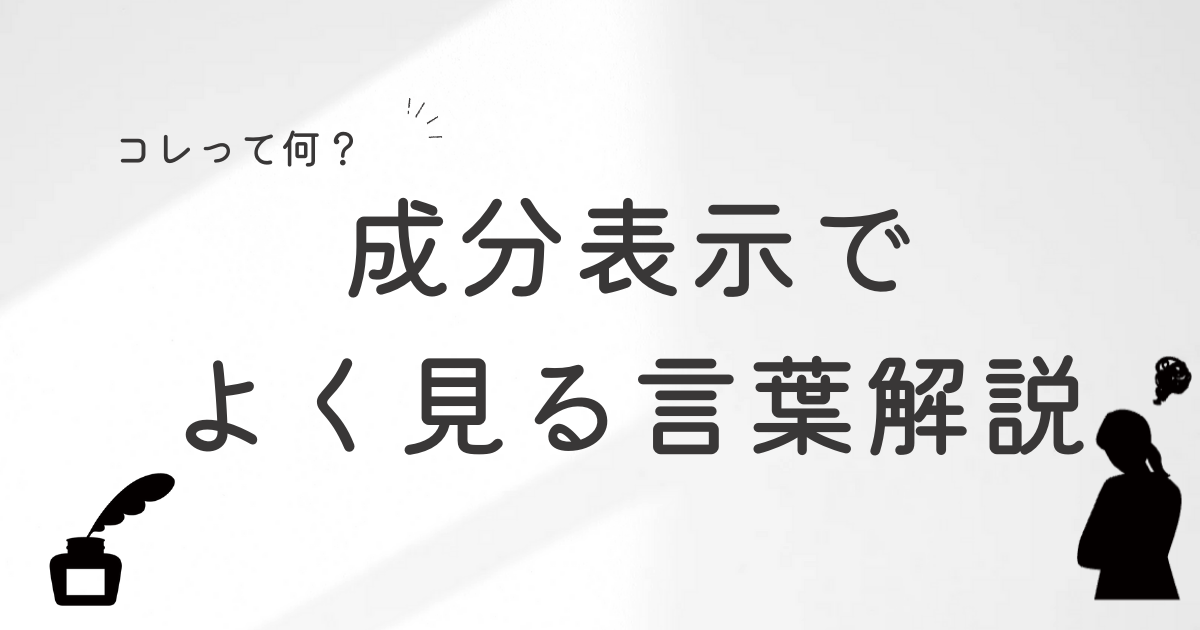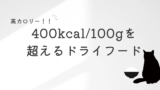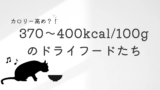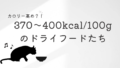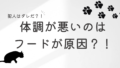そのキャットフード、何が入ってるか理解できていますか?

猫の健康を守るうえで、キャットフード選びはとても重要ですよね。
でも、パッケージに並ぶ専門用語や成分表示を見て「結局どれが良いのかわからない」と感じたことはありませんか?
そんなみなさまに向けて、フードを“見極める目”を持てるようになるヒントを集めてみました。
この記事では、キャットフード選びで知っておくと役立つ言葉を、できるだけやさしく・具体的に解説していきます。
成分表でよく見る栄養素の名前と意味
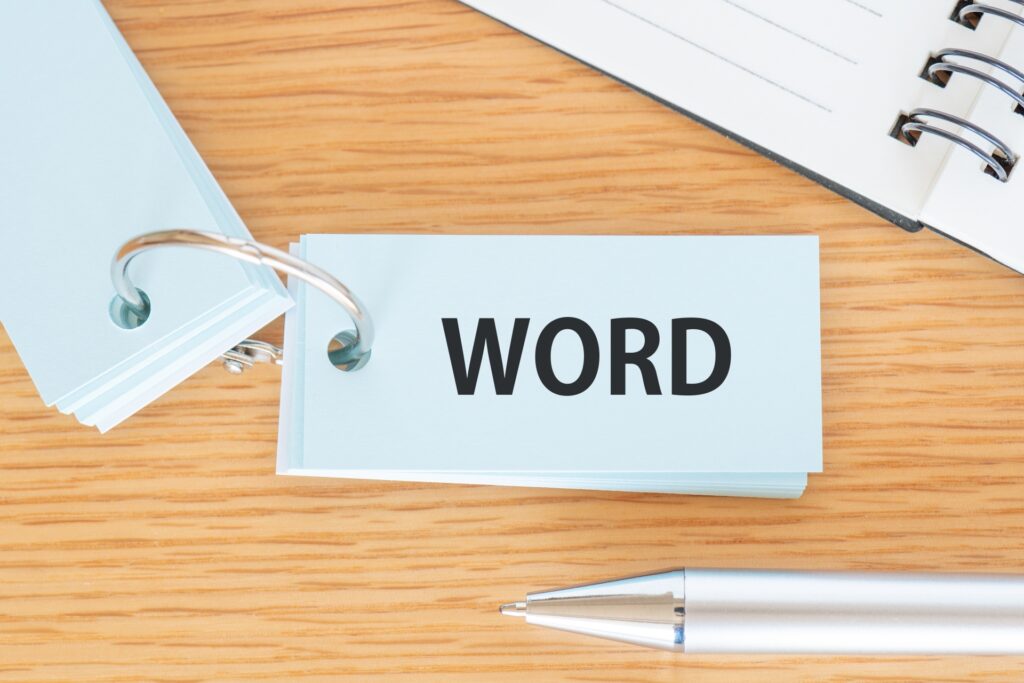
タンパク質(粗たんぱく質)
猫は肉食動物なので、たんぱく質は一番大事な栄養素。筋肉・皮膚・被毛など、体のあらゆる部分をつくる材料になります。
パッケージでは「粗たんぱく質〇%」と書かれており、30%以上が一つの目安です(ただし、猫ちゃんの年齢や体型によって適量は異なります)。
原材料リストに具体的な動物性タンパク質が記載されているものを選びましょう。具体的には「チキン」「ターキー」「サーモン」など。
脂質(粗脂肪)
エネルギー源として必要な栄養。脂質がしっかり摂れていると、ツヤのある毛並みや元気な活動量にもつながります。
ただし、高カロリーフードの場合は与えすぎに注意。成猫であれば15〜20%前後がを目安に。
粗繊維
消化を助けたり、便通を整えたりする役割。
与えすぎると栄養の吸収を妨げることもあるため、2〜5%程度が適量とされています。
灰分
ミネラル(カルシウムやマグネシウムなどの無機質)をまとめた指標。多すぎると尿路結石の原因になる場合があるので、7%未満がひとつの目安。
水分
ドライフードでは水分は10%以下が一般的。水分量が少ない=長期保存しやすいですが、水分摂取が少ない猫は泌尿器に注意が必要です。
糖質(炭水化物)
猫にとって必須栄養素ではありませんが、エネルギー源になります。あまりにも多いと肥満の原因に。
糖質が多すぎる場合、原材料の前半に「コーン」「米」「じゃがいも」などが並んでいることが多いです。
グレインフリーのフードであっても、ジャガイモやタピオカなどの炭水化物が多い場合があります。これらも猫にとってはあまり良い選択ではない場合があります。
要チェック!知っていれば安心な“ミネラル”たち

ナトリウム
体内の水分バランスや神経の働きに関わるミネラル。摂りすぎると高血圧や腎臓負担に繋がることがあり、特にシニア猫や腎臓ケアが必要な猫には注意。
カルシウム
骨や歯を作る大事なミネラル。リンとバランスよく含まれていることが重要で、カルシウム:リンの比率は1.1〜1.5:1が理想。
マグネシウム
結石の原因としてよく知られていますが、神経や筋肉の健康にも関わる重要な栄養素です。
少なすぎても多すぎてもダメなので、成猫なら0.08〜0.1%程度が目安。
リン
カルシウムとセットで骨の形成に必要。過剰摂取は腎臓の負担になるので、バランスが大事。
オメガ3脂肪酸(EPA・DHAなど)
青魚や亜麻仁油などに含まれる抗炎症作用のある脂肪酸。皮膚トラブルの予防や、シニア猫の脳の健康維持にも。
オメガ6脂肪酸(リノール酸など)
皮膚のバリア機能を高め、毛ヅヤや肌の健康をサポートする脂肪酸。オメガ3とバランスよく含まれていると◎。
知っておくと安心!パッケージでよく見る用語の意味

サイリウム(サイリウムハスク)
サイリウムとは、オオバコの種皮から取れる天然の食物繊維のことです。水を含むとゼリー状にふくらむ性質があり、キャットフードでは以下のような目的で使われます。
- 便のかたちを整える(軟便・便秘どちらにも)
- 毛玉の排出を助ける
- 血糖値の急上昇を抑える効果もあるとされている
特にお腹が弱い猫や、シニア猫にもおすすめの成分です。
フェカリス菌(エンテロコッカス・フェカリス)
フェカリス菌は乳酸菌の一種で、プロバイオティクス(善玉菌)として知られています。
他の乳酸菌と比べて粒子が小さく、腸の奥深くまで届きやすいのが特徴です。
キャットフードに含まれる目的は、
- 腸内環境の改善(善玉菌の増加)
- 免疫力のサポート
- 軟便・便秘の予防
など。フェカリス菌は加熱にも比較的強く、ドライフードとの相性も良いため、近年注目されている成分です。
クランベリー
クランベリーは果物の一種で、猫にとって直接的な栄養源ではないものの、泌尿器の健康サポート成分として多くのキャットフードに配合されています。
- 尿を弱酸性に保つ働きがある
- 細菌の付着を防ぎ、膀胱炎や尿路感染症の予防に
- 抗酸化作用で老化防止にも効果が期待される
特に、ストルバイト結石になりやすい猫にとっては、クランベリーが役立つことがあります。
しかし、何もトラブルのない子にとっては、尿を酸性方向に傾けることがよいとは言えない場合もありますので、そのあたりはお忘れなく。
尿路トラブルと関連ワードも知っておこう

ストルバイト結石
ストルバイト結石は、リン酸アンモニウムマグネシウムが尿中に結晶化してできる結石のことです。
尿がアルカリ性に傾きやすい猫に多く、オス猫に特に注意が必要です。
ストルバイト対策のために意識すべきポイント:
- マグネシウム・リンの摂取量をコントロール
- 尿pHを弱酸性に保つ(クランベリーなどの成分が有効)
- 水分をしっかり摂る(ウェットフードや水分補給の工夫)
シュウ酸カルシウム結石
シュウ酸カルシウム結石は、ストルバイトとは逆に、尿が酸性すぎるとできやすい結石です。
こちらは高齢猫や泌尿器疾患を経験した猫に見られることが多く、カルシウムやビタミンDの過剰摂取が原因となる場合もあります。
※どちらの結石も、「クランベリーを含むから安心」とは限りません。猫の体質に合わせて、成分のバランスを見ることが大切です。
ことばを知ることは、愛猫の健康を守る第一歩

キャットフードの裏側に書いてある“あの成分”も、“この言葉”も、意味がわかれば選ぶ基準がグンと明確になります。
とくにサイリウムやフェカリス菌、クランベリーのような“ちょっとマニアック”な成分を理解できると、プレミアムフードの真価が見えてくるかもしれませんね。